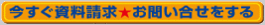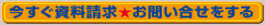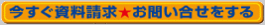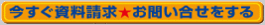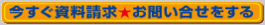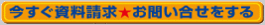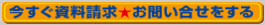地震に備えて耐震診断と耐震リフォームをしませんか?
●地震から命を守るためには、建物の倒壊を防ぐことが一番です。
しかし古い住宅では耐震性が現在の基準に比べて低いものが多く、大地震が起こったときに倒壊する危険性があります。
そこで耐震補強工事を行い、住宅の耐震性を高めて、あなたと家族の命や財産を守るのが「耐震リフォーム」です。
最近、地震が多発する傾向にあり、リフォームや新築住宅でも地震対策の必要性が強く認識されるようになりました。
*************************************************
【1】 耐震性に不安がある家とは・・・
■日本の全ての住宅は、建築基準法に従って建てられています。
建築基準法は昭和25年(1950年)に制定されました。
その建築基準法の耐震基準は、大きな地震が起きるたびに改定され、強化されています。
したがって、
あなたのお家の耐震性は、いつ建てられたかと言う建築時期を目安にすれば、ある程度判断することが出来ます。
【1】 昭和55年(1980年)以前に建てられた住宅は・・・
■昭和56年に新耐震基準が施行されましたが、それ以前(旧耐震基準)の住宅は、建物の老朽化が進み、
1 耐力壁量が不足している
2 耐力壁の配置バランスが悪い
3 接合部の金物補強が無い
4 基礎が弱い
5 葺き土の上に重い瓦が載せられている
6 土塗り壁で筋交いが少ない
と言うような建物が多く、耐震性の低い住宅が多くあります。
【2】 昭和56年〜平成12年(2000年)までに建てられた住宅は・・・
■昭和53年に発生した宮城県沖地震を受けて、昭和56年に「新耐震基準」が施行されました。
1 軟弱地盤では鉄筋コンクリート基礎が義務づけられた
2 木ずり壁の壁倍率の再評価と面材耐力壁(構造用合板、石膏ボード)の追加
など、必要壁量が大幅に強化され、耐震性が格段にアップしました。
【3】 平成12年以降に建てられた住宅は・・・
■平成7年の阪神・淡路大震災で新耐震基準の住宅は、その強さを証明されましたが、建物の間取りや形状、壁の配置バランスの悪い建物は、倒壊したり、半壊したものも少なからず見受けられたため、平成12年に建築基準法改正がありました。
1 地盤の強さに応じた基礎形状の規定
2 バランスよく耐力壁を配置するための数量化の規定
3 強い引き抜き対策金物を使用する規定
など、基準がさらに強化されました。 このように耐震基準が変わりました。
したがって、あなたのお家の築年数が分れば、耐震性の程度が推測できます。
【2】 あなたのお家で、こんなことはありませんか?
●家の間取りや構造によって、地震に強い家と弱い家があります。
人間は誰しも「自分の家だけは大丈夫」と思う傾向がありますが、自分の命のかかわることですから、住んでいる方ご自身で耐震について考えて見ましょう。
あなたが住んでいるお家で、次のようなことはありませんか?
【1】 柱や壁が少ない
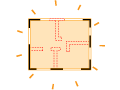
基本的に、木造住宅は柱と壁が建物を支える役目をしています。
壁が少ないと、地震が起きたときに、柱や梁が建物の
重さに耐え切れなくなり、傾いたり壊れたりすることがあります。
【2】 ピロティがある
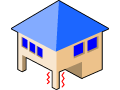
建物の1階に住居をつくらず、柱だけを残して、エントランスホールや駐車場として使用するときの1階部分を「ピロティ」といいます。
地震に対する抵抗力となる壁が少ないので、設計には適切な配慮が必要です。
【3】 壁が偏在している
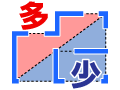
壁の量が、片側に片寄って配置されていると、地震が発生した時に「ねじれ」が起こり、壁が少ない部分の柱が大きく振られて、壊れてしまうことがあります。
建物の柱や壁は、バランス良く配置されていることが望まれます。
【4】 大きな吹き抜けがある
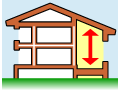
一辺が4mを超えるような、大きな吹き抜けがあると、地震時に建物を大きくゆがめる恐れがあります。
床は建物の強度を大きく左右するので、床がない部分が多いと、それだけ地震にも弱くなってしまう可能性が高いのです。
【3】 あなたにもできる簡易耐震診断
●一般の人がご自宅の耐震性能を理解し、耐震の知識を習得する手始めの資料として、(財)日本建築防災協会編集、国土交通省住宅局監修の「耐震診断問診表」があります。
この診断は耐震診断を受ける前にまずわが家の現状を把握しておくための簡易的な診断です。正確な耐震診断は専門家に依頼し、診断を受けてください。
【1】 耐震診断問診・・・

チェック1・・・建てたのは1981年6月以降である。

チェック2・・・大きな災害に見舞われたことがない。

チェック3・・・増築の際に建築確認などの手続きをした。
または増築していない。

チェック4・・・傷んだ所はない。または傷んだ所は補修し、健全である。

チェック5・・・建物はどちらかというと長方形に近い平面である

チェック6・・・1辺が4m以上の大きな吹き抜けはない。

チェック7・・・2階外壁の直下に1階の内壁または外壁がある。または平屋建であ る。

チェック8・・・1階外壁の東西南北どの面にも壁がある。

チェック9・・・比較的重い屋根葺材であるが、1階に壁が多い。
または、比較的軽い屋根葺である。

チェック10・・・鉄筋コンクリートの布基礎または、ベタ基礎・杭基礎である。
【2】 診断結果:チェックした項目はいくつありましたか?

10項目すべて・・・・・ひとまず安心です。念には念を。
専門家の診断を受け改修箇所の早期発見を心掛けましょう。

8〜9項目すべて・・・専門家の耐震診断を受け、わが家に最適な耐震改修を考えましょう。

7項目以下・・・・・・・とても心配です。
地震がきてからでは遅いのです。
早めに専門家に診てもらいましょう
少しでも気になることがありましたら、当社までご連絡下さい。無料でアドバイスさせて頂きます。
(注) この診断では地盤については考慮しておりませんので、ご自宅が立地している地盤の影響については専門家にお尋ねください。
【4】 専門家による精密診断の実施
■簡易診断は,あくまでも一般の人の耐震に関する意識の向上、耐震知識の習得を目的としたのもで、より専門的な診断へ繋げようとするものです。
耐震補強工事を行うためには、専門家によるしっかりとした耐震診断が欠かせません。
例えば、手抜き工事で基準通りの工事をしていなかったり、基準通りの工事をしていても、メンテナンスが悪く、雨漏り、シロアリ等により建物が予想以上に老朽化している場合がありますから、実際の建物を見て確認しなければいけません。
ポイント 1・・・業者選びについて
■精密な耐震診断をするためには建築知識があり、信頼のおける建築会社を選ぶことが重要です。
最近は、直接自宅を訪問して虚偽の説明をして不安がらせたり、断ったにもかかわらず「このままだと危ない」と耐震リフォームを強引に勧誘する「点検商法」の被害が増えているので注意してください。
ポイント 2・・・契約について業者選びは自己責任です。
■工事を行う場合は、契約の前に契約内容やアフターサービス、保証、工期、クーリングオフなどについて、納得するまでしっかり確認しましょう。
一般的に悪質な業者は、契約を急ぐ傾向があるので、業者のペースに乗せられて失敗しないように契約は慎重にしましょう。
ポイント 3・・・補助について
1 各市町による耐震診断や耐震改修への補助を行っている場合があります。
2 耐震改修を行った場合は、税の優遇措置が受けられる場合があります。
固定資産税額の減額措置、所得税額の特別控除
3 住宅金融支援機構の耐震改修工事融資を利用できる場合があります。
これらについては、建築会社の営業マンに問い合わせると良いでしょう。
ポイント 4・・・ 現地調査のポイント
精密診断で最も大切なものは現地調査です。
診断の当日は、家の外周部や建物内の全ての部屋、床下、屋根裏に入って調査するため、事前に荷物を整理し、動かしておきましょう。
また、荷物の移動や過去の状況をお聞きしたり、部分的に解体して確認する必要性が出てくる場合があるので、一緒に立ち会いましょう。
・・・・・現地周辺調査 ・ 建物外周調査 ・ 基礎の調査 ・ 室内の調査 ・ 小屋裏の調査・床下の調査
精密診断の結果を診断書としてまとめ、後日、現状の説明をさせて頂き、必要に応じてその対策も提案させて頂きます。
【5】 診断結果による耐震補強について
ポイント 1 ・・・ 建て替えと耐震補強について
建物の耐震性は、各家の地盤、基礎、建物の形、壁の配置、筋交い、壁の割合、老朽度等によって異なるので、当然その対策も違います。
1、一般的には、昭和56年以前の建物は、補強工事をしても、技術的に直しきれない部分的欠陥が多くあり、耐震性を確保するには限界があります。
また、補強工事費も建て替えに近い位高額になるので、地震から命を守る最大の解決策は「建て替えること」と言われています。
2、昭和56年〜平成12年に建てられた住宅は、診断結果の評価は比較的高いので、必要に応じて耐震補強をすると良いでしょう。
但し、耐震補強をしたからと言って、絶対に「安全」ということは言えません。
その証拠に、過去に大きな地震が来る度に、国は耐震基準を強化しています。
自然現象で想定以上の地震が来れば、仕方の無いことです。
ポイント 2 ・・・命を守る耐震改修について
■死者、行方不明者が6400人以上にものぼった阪神・淡路大震災で、
・ 地震発生後約15分以内に約92%が亡くなっている
・ 死因は窒息死が全体の54%、圧死が12%
これによると建物の倒壊や家具の転倒、落下で一瞬にして身動きできなくなったと考えられます。
すなわち、本来命を守るべき家が命を奪ったと言うことで、すぐに倒壊しなければ、避難することは可能で、命だけは助かった可能性が高いと言うことです。
このことを考えたとき、家の耐震性に不安があれば、現行の耐震基準に合った耐震性の高い家に建て替えることが理想です。
しかし、その費用が負担できないとしたら、予算の範囲内で耐震改修をして、少しでも現在の家の耐震性を向上させることが大切です。
■地震が自然現象であり、自然は人間の想像をはるかに超えた力があります。
したがって、新耐震基準で建て替えたり、既存住宅を耐震診断の評点1.0以上になるように耐震改修をしたとしても、決して「安心です」と言い切ることは出来ません。
しかし、一瞬の内に倒壊しなければ、非難は出来るし、命が助かる可能性は高くなります。
だから、わずかな補強でも、現在よりマイナスに働くことはありません。
地震改修をする場合は、最優先して補強するべき個所がどこかを判断することが重要です。そして、予算のないときでも、最低限の補強はしたいものです。
ポイント3・・・耐震補強工事と綺麗にするリフォームの同時施工で割安に
耐震補強工事をするときは、外壁や内壁を撤去することが多いので、ついでに「綺麗にするリフォーム」 「断熱リフォーム」もすれば、費用を抑えることが出来ます。
反対に 「綺麗にするリフォーム」 をするとき、外壁や内壁を撤去するのであれば、ついでに耐震補強工事、断熱リフォームをされることをお勧めします。
同時にすれば、解体や復旧の作業は共通なので、費用を抑えることが出来、綺麗に、より快適になるだけでなく、将来にわたって、安心して住める家になります。
ポイント 4・・・補助制度について
国は平成27年までに住宅の耐震化率9割を目標にし、地方自治体は耐震改修工事に対して補助金制度を準備していますが、既存住宅の耐震化が進んでいないのが現実です。
その理由として、次のようなことが考えられます。
行政が耐震改修工事費用を補助する制度は、改修後の性能として新耐震基準レベルを求めていることが多いからです。
そのためには、いくら補助をもらっても、予算が掛かりすぎるので、工事自体を諦めることになるのです。
【6】 耐震補強工事の方法
【1】 壁の補強について
一階の壁を補強することは、建物の倒壊を防ぐのに最も有効な手段です。
しかし闇雲に補強しても偏心率(重心と剛心に距離)は改善されないので、的確な位置に筋交いを入れたり、構造用合板を用いて補強することが大切です。
【2】 接合部の補強について
接合部を金物補強する場合は、バランスよく補強することが大切です。
基礎と柱や土台、柱や梁の継ぎ手、仕口 、筋交いの端部を色々な金物で緊結します。
【3】 屋根の軽量化について
古い建物は重たい屋根が多く、重量のある日本瓦を軽量のコロニアルや金属製屋根材に取り替えることにより、壁の補強と同じ効果があり、耐震性が向上します。
【 4】 床下の湿気対策について
床下の湿気が多いと腐朽菌による腐朽やシロアリによる食害により、建物の構造体が弱体化し、地震等により倒壊する可能性があります。
したがって、湿気が多い場合は、適切な除湿対策を講じる必要があります。
【5】 基礎の補強について
基礎に鉄筋が入っていない場合は、既設の基礎に鉄筋コンクリート造の基礎を抱き合わせて一体化して補強します。
【7 】 誰でも出来る我が家の地震対策
費用を掛けて耐震改修をすることも大切ですが、その前に自分たちで出来る簡単な地震対策があります。
【1】 家具の配置と固定について
1 家具が倒れないように固定し、逃げるときの避難路を確保する。
2 家具が倒れたときに、下敷きにならないような位置で就寝する。
3 観音開きの扉には止め金具を付ける。
4 子供や高齢者にいる部屋は大きな家具は置かない。
5 窓や食器棚などの硝子に悲惨帽子フィルムを貼る。
6 家電製品やピアノ等を固定する。
【2】外回りについて
1 エアコンなどの室外機がしっかり固定してあるか確認する。
2 植木鉢やプランターが不安定になっていないか確認する。
3 瓦のズレ、外壁のひび割れ、基礎の亀裂、シロアリの被害等が無いか確認する。
4 避難経路が確保されているか確認知る。* ブロック塀等の強度を確認する。