自然素材について
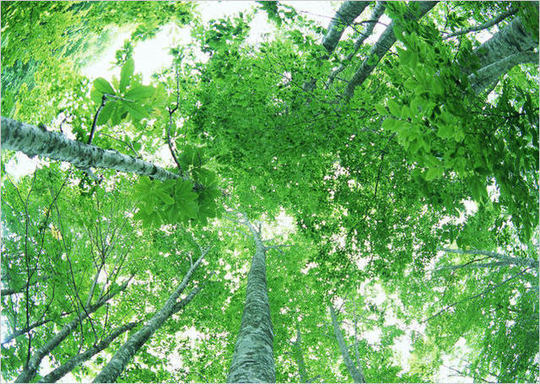
「健康のことを考えて、自然素材をふんだんに使った家を建てたい!」とお考えのお客様は多くおられます。
「自然素材を使った健康住宅」と言うと、天井も壁も全て天然ムク材を使った家を思い浮かべます。
「木に囲まれた生活はリラックス出来ていいなあ!」と思われるかも知れませんが、意外と問題点や落とし穴があるのをご存知ですか?
普通の会社はこんなことは言わないでしょうし、勿論他社のホームページをご覧になってもデメリットはほとんど書いてないと思います。
しかし私たちは正直に全ての情報を開示して、後はお客様のご判断にお任せするという考え方ですから、続けてお読みください。
問題点1.どうしても「割高な家」になってします
- 材料費が割高になる
自然の材料だから見栄え、品質にバラツキがあるので、見栄えや品質を揃えようとすると、選別しなければならなくなり割高になります。
例えば床材を、建材店や材木店から見本を取り寄せて確認して「良い」と思って注文しても、品物が届いて梱包を開いてみないと「良いかどうか?」分かりません。
また1つの梱包の中でも「不揃い」があり、梱包が複数のときは全ての梱包を開いてみないと、使って良いかどうか分かりません。
自然の材料が枯渇すれば、価格も高騰し、同じようなものは手に入らないこともあります。これが自然素材の難しさです。
- 工事費が割高になる
材料が均一でないので施工が難しくて職人さんの手間が多くかかり、工事費が割高になります。
問題点2.ホンモノとニセモノの区別
自然素材の良さが認識され、多く利用されていますが、クレームも増えています。
そう言うクレームを少なくするために、自然素材の生産者は「科学の力 ! ?」で色々な特殊加工をしたり、添加物を加えて新製品を開発し販売しています。
その結果、見た目は同じでも本来自然素材の持っている機能が失われていたり、安全性に疑問がある建材 が出回っているのも否定出来ません。
(でもこの問題は勿論生産者に問題があるのですが、自然の特性を理解しない消費者の過度の要求にも問題があるのではないでしょうか…?)
- 珪藻土のヒビ割れを防止するために、合成樹脂を混ぜるため、珪藻土の細孔が詰まって折角の機能(調湿、消臭、有害物質の吸着など)を殺している商品
- 自然素材の畳ではあるが、農薬を多量に使ったり、防虫の薬剤処理をした商品が出回っているが、見分けが付かない。
(虫などが出るということは薬を使っていないということで、ある意味で人が安全だとも言えるのですが…半断の難しいところです。)
- 日本伝統の塗り壁材の漆喰(しっくい)は体に無害と考えられていましたが、石灰石を焼いて作るので、発ガン性の疑いがあると言う研究結果が最近発表されました。
このように、自然素材を使う時は十分な注意と理解が必要です。
問題点3.自然素材の経年変化について
温度や湿度、日照などの環境条件によってヒビ割れ、狂い、色の変化などは自然素材の特徴、持ち味なのです。
しかし日本人の国民性かも知れませんが、「きれい、均一」なものが美しいと言う美的感覚があり、きれいで均一しかも安価な工業製品が氾濫しました。
そこで自然素材に接する機会が少なくなり、それに対する理解もあまり無いので、実際のものを見ると「自分のイメージと違う!」と言うことでクレームになることが有ります。
例えば…
- 1構造材など木材のヒビ割れ、隙間
- 2木材に多くの節が有り、見られているような気がしたり、自分のイメージと違い気になる。
- 3床材などの隙間、反りとこれらによる床鳴り
- 4「ドアが閉まらなくなった!」など建具の狂い
- 5木材や畳に発生するカビやダニ
- 6日常生活で付くムク材の傷、隙間や塗り壁のヒビ割れ
これらの大部分は仕方のないことなので、経年変化を楽しむという感覚が大切です。
したがってこのようなことが嫌な人は、絶対に自然素材を選んではいけません。
また建築会社も事前によく説明し、出来れば現物を見て納得して頂く様な配慮が必要です。
問題点4.木視率100%はキツイ!
「木視率・ もくしりつ」という言葉をご存知ですか?
木視率とは室内を見渡した時、木が見える割合のことです。普通の家で木視率20%前後と言われています。
木視率30%、45%、90%の3タイプの部屋を作り、視覚による快適感を調査したところ、特に45%の部屋が最も好まれました。
脈拍数は30%の部屋で少なくなり、45%の部屋では増加しました。
これは、30%の部屋は「リラックスしている」45%の部屋は「ワクワクした状態」になっていると考えられます。
このような結果から寝室は木視率30%、リビングは木視率45%が最適だと考えられます。
また、50%を越えるとクドイ、うっとおしい、落ち着かないと不安感を感じる人もいます。
中には寝ていて天井の木の節が気になって寝られなかったり、自然素材特有の「不揃い」が気になる方も居られます。

このように自然素材にこだわった家づくりは、どうしても割高になるし、自然素材特有のデメリットがあります。
しかしお客様の中には 「100%自然素材は落ち着かないので、そこまでしなくても…」とか「限られた予算の中で、少しでもいいから自然素材を取り入れた家に住みたい!」という方も居られます。
そこで当社では「こだわりの場所」に部分的に自然素材を使うことをお勧めしています。
例えば、家族みんなが集うリビングだけとか、子供部屋だけムク材のフローリングにするということでも良いのではないでしょうか?
それに部分的に珪藻土などの塗り壁や紙クロスなどを組み合わせると、木視率100%の家よりは、変化が出てオシャレな家になります。
このように予算とこだわりによって適度な木視率になるように部分的に自然素材を使い、残りの部分は当社標準仕様のSODリキッド工法でシックハウス対策をすれば、室内環境は改善されます。

また、抗菌・殺菌作用やアトピー性皮膚炎の大敵であるダニや細菌の繁殖をおさえる働きがあります。
住宅建材としても大変丈夫で、日本の古い木造建築(寺院など)がその強度を証明しています。
一方、自然な木ですから、月日が経つに従って色が変わってきたり、乾燥によるひび割れ、虫穴などもあります。
しかし、それこそ天然の証であると思っていただければと思います。
| ヒノキ | 高級木材の代名詞。年輪幅の細い美しさと独特の香りが特徴。 耐水性に優れ構造材から内装まで幅広く使われている。 |
|---|---|
| スギ | 国内で一番多く植林されている。 加工性に優れ用途が広い。比較的リーズナブルな素材 |
| ヒバ | 殺菌性の強い精油成分を含む。構造材、内装材、家具や水廻りに使われる。 |
| マツ | やわらかい印象のアカマツ、ヤニが多く年輪がくっきり浮かび上がるカラマツがある。 |

2.炭…木炭、竹炭
近年床下に木炭を敷き詰める住宅が増加しています。
これは木炭が持つ調湿効果や脱臭の他に、有機化合物質を吸着する効果が有るからです。
床下の乾燥によって木材の腐食を防ぎ、シロアリ対策となり、畳も除湿されることによってダニ類の発生を防ぐ効果も生まれる為です。

また木炭の粉を原料とした木炭塗料は基礎や、木材に塗布することによって、防腐、防蟻、空気質改善効果があるとされる商品もあります。
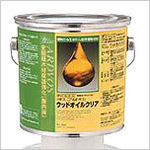
3.天然塗料…リボス、柿渋、亜麻仁油、木炭塗料
どんなに建材を自然素材にしても、塗料がよくなければ健康住宅とは言えません。
従来、塗料は石油・シンナーなどの有機溶剤を原材料としたものが多く、トルエンやキシレンなどの有害な化学物質を含んでいます。
低濃度でも長い期間吸い続けると慢性中毒を引き起こす有機溶剤を住宅には使いたくないものです。
そこで、シックハウス対策として天然系塗料が注目されています。天然塗料には、世界的に有名なドイツのリボス社のリボスがあります。
その他には蜜ロウワックス、亜麻仁油、柿渋などがありますが、価格が高く、作業性が悪いという問題があります。

4.珪藻土・漆喰
珪藻土の「珪藻」とは植物性プランクトンのことで、珪藻土とは珪藻の殻の部分が何千万年にわたって蓄積してできた化石のことです。
1ミクロンにも満たない小さな孔が無数にあり、それにより優れた呼吸性を保ち、調湿、消臭の効果を発揮します。
また火に大変強く、摂氏1250度までは形状が変わりません。
ただし、色々な珪藻土が商品化されていますが、本来の機能や効果の期待できないものもあるので注意して下さい。
漆喰(しっくい)日本の伝統的な塗り壁材で、石灰石を焼いた生石灰を水で沸化させた消石灰に湖・スサなどを混ぜて練り合わせたものです。
暖かく、やわらかみのある風合いが特徴ですが、近年、発ガン性があるという研究結果もあるので、注意して下さい。
5.畳
近年の畳の主流はポリスチレンフォームをワラで包み、イグサの畳表を張った化学畳です。
これは軽くて手軽な反面、化学物質過敏症の原因となり、焼却処分の際には有害物質を発生させます。
従来の畳はワラ床にイグサの畳表を張ったもので、化学畳に比べ重いが、吸湿性、遮音性に優れているものの、ダニの温床となりやすい欠点があります。
また、防虫、防ダニ加工としてナフタリンや有機リン系の農薬を染み込ませているものもあるので注意してください。

6.ケナフ壁紙
「ケナフ」とは、アオイ科ハイビスカス属の1年草です。
春に種をまくと、秋には3〜4mになり、薄黄色の花を咲かせます。
1ヘクタール当たり10〜15tの「ケナフ」が収穫でき、木材の4倍量の紙ができます。ケナフの使用用途としては、ハガキ・包装紙・紙コップ・名刺など多数あげられます。
そういった中で、「ケナフ壁紙」が商品化されています。
森林資源保護の観点から、木材パルプの代わりになる紙資源として「非木材」が注目されつつあります。
その中で「ケナフ」が、麦やサトウキビ、綿、コウヅ、ミツマタ、竹、トウモロコシなど他の
ものに比べて、収穫率や品質に優れているため選ばれました。
また、地球温暖化防止のためのCO2削減においても「ケナフ」は木材に比べて多くのCO2吸収量があり、地球環境に貢献しています。
7.アトピッコハウス(株)
アトピー、アレルギーなどデリケートな人が安心して使える自然素材や、ホルムアルデヒドを一切使わない「ゼロホルム建材」を業界に先駆けて開発・販売しています。






